出典元:https://www.amazon.co.jp/dp/B001QD22RE/?tag=cinema-notes-22
伝説の古典的名作として映画史にその名を刻み続けてきた「第三の男」。原作はイギリスの大作家グレアム・グリーンです。
有名なツィター演奏によるハリー・ライムのテーマ、映画そのものを一瞬でさらってしまったハリーの初登場カット、芸術的な光と影の演出。
第二次世界大戦直後のフィルム・ノワールとして製作された本作は時代背景も含め今も尚我々に多くのことを伝え、考えさせてくれるものです。
本稿では最後でハリーに引き金を引いた人物、彼がウィーンに呼ばれた理由や鳩時計の意味など本筋を彩る魅力を中心に掘り下げてみます。
そして、アンナが頑なにハリーを愛し続けた理由を考えてみましょう。
時代背景
大前提として、「第三の男」の根幹を成す歴史的な時代背景について理解しなければなりません。
映画史にその名を轟かせた本作は果たしてどのような世界観の元にお話が成り立っているのでしょうか?
混沌とした戦後のウィーン
「第三の男」の舞台は終戦直後のウィーン、かつてモーツァルトやベートーヴェンなどの天才音楽家が憧れた「音楽の都」です。
ある意味本作で一番の主役といえるかも知れないウィーンは1949年当時そのような華やかさなどまるでありませんでした。
終戦と共にナチスドイツの植民地支配から解放されたとはいえ、当時はまだ米英仏ソ四か国の共同占領下にあったのです。
ウィーンが完全な独立を果たしたは1955年なので、この時はまだ非常に混沌とした街となっています。
その証拠に河川に浮かぶ死屍累々、瓦礫の数々、そして社会の裏で横行する最盛期の闇市場とかなり怖いイメージの映像ばかりです。
他国籍者の物語
もう一つの特徴は舞台がウィーンであるにもかかわらず、主役三名が全て他国籍者、即ち「よそ者」であるということです。
旧友のホリー・マーチンスとハリー・ライムは米国出身、アンナ・シュミットはチェコの亡命者といずれもオーストリア出身ではありません。
しかもウィーンにやって来た目的もそれぞれに全く異なっており、三人は数奇な運命によって複雑に絡みあっていくのです。
ウィーン中央墓地
こうした本作のどこか退廃的で重苦しい雰囲気を象徴するのが、冒頭と終盤で出てくるウィーン中央墓地です。
「墓」というとやはり連想するのは「死」であり、本作はウィーン中央墓地を「ハリーの死」の象徴として用いています。
墓自体は他の映画でも見かけますが、「第三の男」においては戦後ウィーンの退廃的なイメージをより強く印象づけるものなのでしょう。
こうしたロケ地に対するこだわり、画面の豊かさが本作の魅力を物語っています。
ハリー・ライムの魅力
「第三の男」最大の見所はやはりオーソン・ウェルズ演じるハリー・ライムです。
彼は後半~終盤のここぞというピンポイントでしか出てきません。
にもかかわらず、全てをかっさらってしまう彼の魅力について改めて掘り下げてみましょう。
天才と大罪人、二つの顔
ハリー・ライムはオーソン・ウェルズが演じているというだけでその魅力が成り立っているわけではありません。
彼には大きく分けて二つの顔があります。
一つが旧友のホリーが知っている「天才」としての顔、そしてもう一つがアンナの知っている「大罪人」としての顔です。
売れない三流作家のホリーは、自身が決して優れた才能を持ってないからこそハリーの才能と行動力に憧れを持っていました。
一方チェコから亡命してきた女優アンナは、同じ訳ありの犯罪者としての顔を持つ彼のミステリアスさに心奪われ愛したのです。
この「ホリーから見たハリー」と「アンナから見たハリー」という二つの視点がハリーをただの悪人に留めていないのでしょう。
こうした文芸面からの見せ方が優れている所もハリーの魅力を押し上げている確かな要因です。
単なる金の亡者ではない純粋悪
物語後半ハリーはペニシリンを軍から略奪し、水で薄めて高額で販売し子供達を死に至らしめ金儲けを行う大罪人であると判明します。

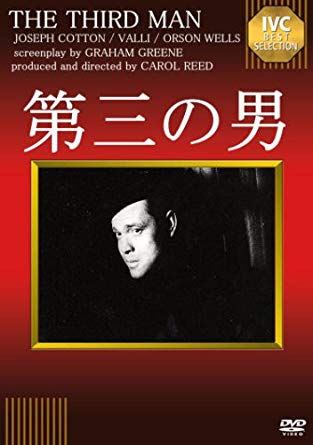
 LINEで送る
LINEで送る





