「食べろ」ということでしょう。
恐る恐る口にしたダンバーでしたが、これこそがスー族とダンバーの関係をより密接にしていきます。
相手の食文化に敬意をもって接することは、どこの世界でも相手を敬う行動の一つです。
インディアン達にとっては文化であり儀式、そして生きる糧なのがバッファロー狩りでした。
ダンバーが獲物を仕留め、肝臓を口にしたからこそより強い『絆』で結ばれたのです。
ツーソックスとダンバー
ダンバーにとってのもう一つ『絆』、それは愛すべき隣人ツーソックスとの絆です。
もっとも孤独な日々
狩りが終わり砦に戻ったダンバーは、今までにない『孤独』を感じます。
素晴らしい仲間がいるのに一人だという『孤独』です。
彼の孤独の根幹は人種です。
彼の心はもはやインディアンでしたが、白人という人種を変えることができないジレンマによる孤独でした。
その夜、狩りの興奮がまだ冷めないダンバーは篝火の周りを踊り狂います。
インディアンたちの儀式の見よう見まねでしょう。
フロンティアで自分の存在を見つめるダンバーと、その姿を見守るツーソックス。
何とも可愛らしく、印象深いシーンとして描かれています。
狼と踊る男
友達のところに行くのに遠慮は無用だと考えたダンバーは、一人スー族に会いに行こうとします。
そんなダンバーに「一人にしないで」と言わんばかりにツーソックスは絡みついていきました。
大の男が二人でじゃれ合っているように見えるそのシーンが『狼と踊る男』の由来になります。
このシーンはツーソックスへの感情移入を促し、のちに狙撃されるシーンで観客の心を揺さぶるための伏線の一つです。
誇り高き戦い
『こぶしを握って立つ女』に言葉を習い、どんどんスー族を理解していくダンバーに大きな事件が待っていました。
不倶戴天の敵
ダンバーは敵対するポーニー族との戦いに参戦を申し出ます。
しかし『蹴る鳥』は彼の家族を守るという役を頼みました。
家族を預けるというのは、とてつもなく大きな信頼を寄せていないとできないことです。
スー族でのダンバーの立場がよくわかります。
ポーニー族は映画の後半、白人たちに協力してスー族たちを追い詰める部族です。
同じインディアンであるにもかかわらず、なぜそのような道を選んだのでしょうか。
ポーニー族はスー族よりも前に白人に降伏したのですが、協力までするというのは普通ではありません。
それほどまでにスー族を憎んでいたということです。
戦いで得たもの
ダンバーは攻めてきたポーニー族から託されたスー族を守り抜きました。
この時に彼の中で起こった変化とはどのようなものだったのでしょうか。
命を懸け守り抜くという経験は、ダンバーに今まで味わったことのない誇りを感じさせます。
そして『自分』という存在について改めて考えるのです。
そして『ジョン・ダンバー』という名前には何の意味もないことに気づきます。
『狼と踊る男』という新しい名前の中に本当の自分を見出していくのです。
白人には戻れずインディアンにもなれない中途半端な孤独を払拭できた瞬間『こぶしを握って立つ女』に対する思いが溢れました。
そんなダンバーの気持ちに反対するものは、もはやスー族の中にはいません。
一族は祝福と共に『こぶしを握って立つ女』を妻にすることに賛同しました。
『風になびく髪』が彼女の前夫について話す場面の演出は素敵です。
そこにはダンバーへの信頼が友情以上のものを感じさせました。
ダンバーは『信頼できる男』から『家族』に昇格したのです。
ダンバーの決断
白人が来て何をするつもりなのかを打ち明けるのは『家族』になったダンバーにとっては当然のことです。
日記を取りに帰って捕まったダンバーは、聞く耳を持たない白人に対しスー族の言葉で話しました。

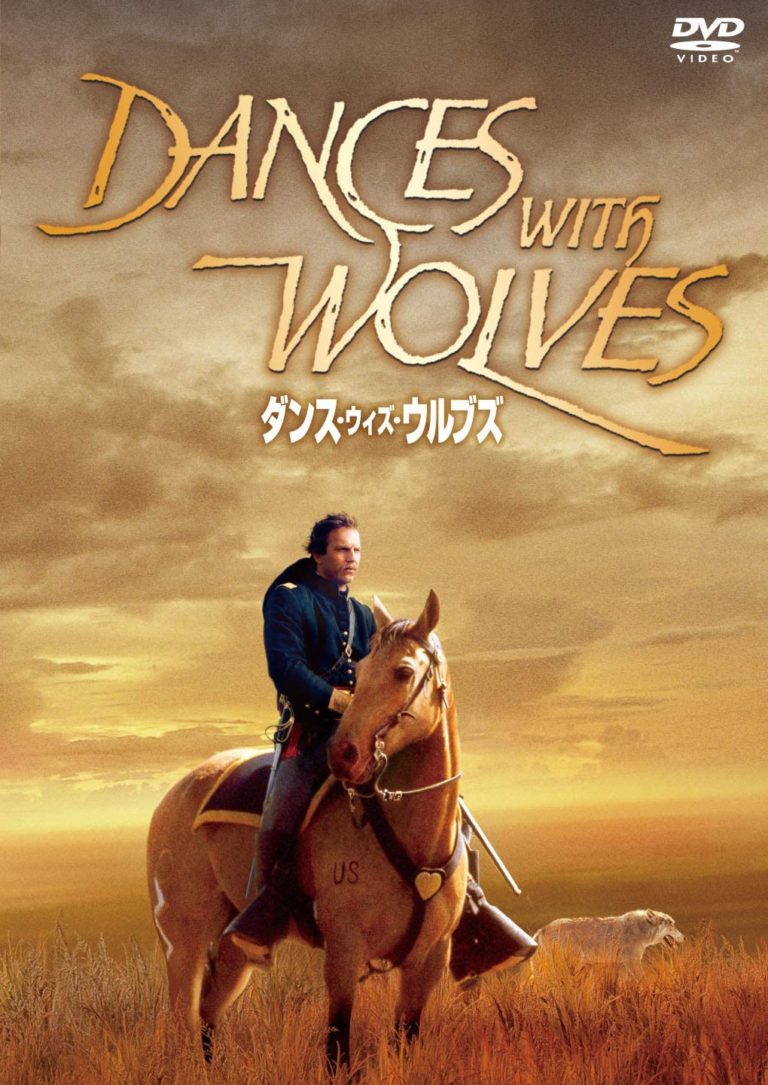
 LINEで送る
LINEで送る
![Dances with Wolves [DVD]](https://cinema-notes.com/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)




