ワトソンは人を心底信じることが出来る男でもあったのです。
こうして心が通じ合い、政府とプレスに対する宣戦布告となったのです。
ワトソンは「真実」が分かっているのでリチャードを信用することが出来ました。ポリグラフもリチャードは嘘をついていないと証明しました。
その「真実」を持ってすれば政府だろうがメディアであろうが怖くはない、「正しい事」は必ず理解されるのだ、と。
裁判に持っていったら大変なことになる、逮捕と起訴を避けるためワトソンは記者会見を設け、ボビに涙の声明を読ませます。
こうしてFBIがなかなかリチャードを逮捕出来ないこともあってメディア・リンチは沈静化、FBIのギブアップに繋がっていきました。
「おまえはクロだ」
FBIがリチャードを容疑者リストから外したとする手紙を持ってきた時のショウ捜査官の捨て台詞です。
ショウはまだリチャードを犯人だと本当に信じ切っているようです。
その後真犯人が分かるのですが、この時点では彼はまだリチャードの「真実」に目を向けようとしないのです。
激しい思い込みから離れることが出来ないでいるわけです。ショウは人を心底信じることが出来ないんじゃないのか、そう思わせます。
彼の哀れな一面をみる思いですが、こうした捜査官がその後も働いていると思うとゾッとするところでもあります。
一方、そうしたショウ捜査官の存在が、リチャードを信じているワトソン弁護士の存在を更にクローズアップする効果を生んでいます。
女性記者の描き方
メディア・リンチの口火を切った地元紙女性記者キャシー・スクラッグス(オリヴィア・ワイルド)の描き方には賛否あります。
FBI捜査員から枕営業をして情報を取ったというのは真実ではない、という抗議も製作側は受けています。
暴走するメディアの権化のような人物として描かれ、メディアの立ち位置を鮮明にする一定の役目は果たしているといえるでしょう。
ただ、事実かどうか不明な彼女の色仕掛け作戦を敢えて表現することは必要なかったのではないか、とする声も少なくないのです。
「真実」をテーマにしていながら「真実」であるかどうかが分からない事を映画に入れることが脚色とはいえどうなのか、という指摘です。
また、イーストウッド自身、あれだけの冤罪事件を起こしたのにメディアは騒ぐだけ騒いでその後の報道は少ないと苦言を呈しています。
その割には、キャシー記者などのメディアの横暴に対するカタルシスを感じられないと指摘する人もいます。
消せないタッパの番号
リチャードの嫌疑は一応晴れて、FBIから家宅捜査の際に押収された母ボビのタッパウェア。
押収物には全部ナンバーがマジックで書かれていて、タッパの蓋の数字も消すことが出来ません。
元に戻ったように見えたリチャードの決して事件の前に戻れない社会的な状況のメタファーとして見事に描かれています。
FBIの容疑者リストから外れ、逮捕も無くなったわけですが周囲の見る目はかつての「英雄」を尊敬するそれではなくなりました。
FBIのプロファイリングだけに頼った見込み捜査とメディア・リンチは一人の男の人生を壊してしまったのです。
SNS社会になり、こんにち誰もが簡単に情報を発信出来るようになりました。
リチャードのような人物を簡単に生み出してしまう危険性はますます大きくなり、実際そのような事件は多く報道されています。
誰もがリチャードになりうる。
誰もが手の中のスマホにSNSという小さな新聞や放送局を持っているという現代。
簡単に加害者になってしまうという厳しい認識を全世界の人が共有することが大切だ、作品からはそうした声が聞こえてきます。

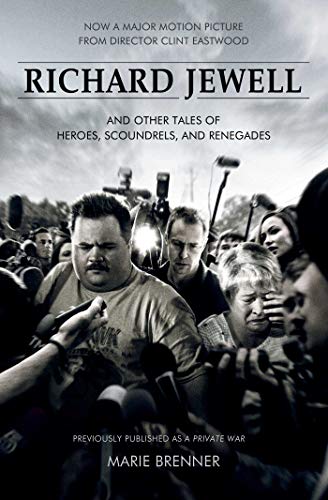
 LINEで送る
LINEで送る





