そうした二人が自殺したウィロビー署長の、それぞれに遺した手紙により大きく方向転換していきます。
なかでもディクソン巡査の変化は目覚ましいものでした。
ミルドレッドが警察署に放火した時、犯人は彼女だと分かりつつ大ヤケドを負いつつもミルドレッドの娘失踪事件のファイルを命がけで守ったのでした。
さらに真犯人に行き着くかも、と酒場で大げんかをしながらも相手を引っ掻いてDNAを採るという行動に出ます。
感情のおもむくままに相手を攻撃してきた二人は署長の手紙をきっかけに「贖罪」に加え、「赦し」が心に芽生えてくるのでした。
“怒りは怒りを来たす”

映画を象徴する一言ともいえる重要なセリフでしょう。
これを主要なキャストではなく、ミルドレッドの別れたDV夫にくっついている19歳の若妻に言わせる演出がニクいです。
他のメンバーが言えば身も蓋もないでしょう。
怒りは怒りしか呼ばない
引用:スリー・ビルボード/配給会社:20世紀フォックス映画
逆に言えば「赦しは赦しを呼ぶ」のです。
まさに本編を貫く思想と思えます。それがきっちりと描かれるのがラストシークエンスでしょう。
真犯人探しに旅立つミルドレッドとディクソン巡査。少し前なら想像もできないシーンです。
「負の力学」から解き放たれ、「赦す」ことで心の平穏を得ることが出来ることを知った二人が交わす笑顔。
これは、お互いを赦すところまでいかないまでも、それぞれの存在をあるがままに受け入れた、というサインだったのではないでしょうか。
そして真犯人は
伏線はあるが結局は
退院したディクソン巡査がバーで聞いた9ヶ月前のレイプ事件。
体を張ってDNAを採ったものの検査では別人とされてしまいます。
しかし、諦めないミルドレッドとディクソンは真犯人がいるかも知れないアイダホ州へと旅立つのでした。
車中で二人は真犯人を見つけた場合、その男を殺すかどうか話し合います。
その時点で犯人を捕らえてどうするか、という点はあまり重要ではなくなっているようです。
この作品はミルドレッドの復讐劇のようにして始まりますが、結局は復讐劇ではないのです。
そして娘をレイプしたのは誰かを探す映画でもないということに気付かされます。
結局真犯人は誰なのかは分からずじまいでいいのです。
マクドナー監督が「人間はだれしも心に中に善なるものと悪なるものが同居している。」
そして「どちらか一つの価値観に縛られてはいけない、一人で生きているわけではないのだから」と言っているような気がします。
そうでなければ監督自身が、自分がこれまで作った作品の中で最も希望に満ちた映画だ、とは断言できないはずです。
全体の味付けを西部劇の復讐話風に進め、それを裏切るかのように人間臭いエンディング。
この手法を持ってきた監督の手腕を(脚本家としての力量も)買わないではいられません。
一見重そうなストーリーですが、ラストで味わうカタルシスは、意味が分かればむしろ清々しい感じを受ける傑作と言えるでしょう。

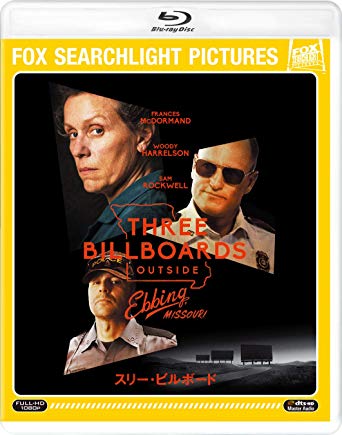
 LINEで送る
LINEで送る




